 まさたこ
まさたここんにちは。aim TENNIS ACADEMY代表の、まさたこです。
今日は、テニスプレーヤーなら誰もが一度は経験したことがあるであろう「相手に飲まれてしまう」という状況について、深く掘り下げていきたいと思います。
この記事を読み終える頃には、「相手に飲まれない強さ」とは何か、そしてそれをどう身につけていくかの道筋が見えていることを願っています。
相手に飲まれるってどういうこと?
テニスに限らず、スポーツ全般で頻繁に耳にする「相手に飲まれる」というフレーズ。これは具体的にどういう状況を指しているのでしょうか?
- 相手の勢いや雰囲気に押されてしまう
- 相手のペースやリズムに巻き込まれる
- 相手の表情やボディランゲージに影響され、自分のプレーが崩れる
- 相手の強気なプレーに対して萎縮してしまう
- 相手のハイテンションに影響されて自分を見失う
これらの状況は、単に技術の問題ではなく、「心の強さ」や「メンタルの自立性」に関わる部分が大きいのです。
私が経験した「飲まれる瞬間」
私自身も選手時代、「相手に飲まれる」経験を何度もしてきました。
特に印象的だったのは、大学時代のインカレ予選での出来事です。相手は高校時代から全国大会に出場していた強豪選手。最初の数ゲームこそ互角に戦えていましたが、徐々に相手の勢いに押されるようになりました。
相手のショットが決まるたびに発する雄叫び、自信に満ちた足取り、威圧的な視線…。それらに少しずつ影響され、私は自分のプレースタイルを忘れ、相手と同じように強打で勝負しようとしてしまいました。
結果は惨敗。試合後、コーチから「なぜ自分のテニスをしなかったのか」と問われた時、答えられませんでした。その時初めて、「相手に飲まれていた」ことを自覚したのです。
「飲まれる」現象の心理学的背景
なぜ人は「相手に飲まれる」のでしょうか?心理学的に見ると、主に以下の要因が考えられます:
1. 同調バイアス(集団同調性)
人間には、周囲の人々と同じように考え、行動しようとする傾向があります。これは「同調バイアス」と呼ばれる心理的傾向です。テニスコート上でも、相手の強いエネルギーや独特のリズムに無意識のうちに同調してしまうことがあります。
2. 自己効力感の低下
アルバート・バンデューラの「自己効力感理論」によれば、「自分はできる」という確信が弱まると、パフォーマンスも低下します。相手の強さを目の当たりにすることで、「自分には無理かも」という思いが生まれ、自己効力感が急速に低下することがあります。
3. 感情伝染(エモーショナル・コンテイジョン)
人は他者の感情状態に影響を受けやすい生き物です。相手の高揚感や自信、時には怒りや焦りといった感情が「伝染」し、自分の感情状態や思考パターンに影響を与えることがあります。
これらの心理メカニズムを理解することで、「相手に飲まれる」現象に対する意識的な対処が可能になります。
プロ選手の「飲まれない力」
世界のトップ選手たちはこの「飲まれる」現象とどう戦っているのでしょうか?
テニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーは、常に自分のペースを保つことで知られています。相手がどれほど激しく感情を表現しようとも、彼はほとんど表情を変えず、自分のリズムを守り通します。
また、ラファエル・ナダルは、独自のルーティン(ボトルの配置、服の整え方など)を試合中に徹底することで、相手のリズムや雰囲気に影響されることなく、自分の世界を保つ術を身につけています。
彼らに共通しているのは、「自分の軸」を守り抜く強い意志です。その軸がぶれないからこそ、どんな相手、どんな状況でも自分のテニスを貫けるのです。
相手に飲まれないために必要なこと
では、具体的にどうすれば「相手に飲まれない強さ」を身につけることができるのでしょうか?ここからは、その具体的な方法について、3つの核心的なポイントをお伝えします。
1. 自分の”基準”を持つ
相手に飲まれる人の多くは、「相手に合わせてしまう」ことが根本原因です。
- 相手が強いショットを打ってくると、無理に同じように打ち返そうとする
- 相手がテンポを上げてくると、そのペースに引っ張られて自分が焦る
- 相手の表情や態度に影響されて、自分の感情が揺さぶられる
しかし、真に強い選手は違います。彼らは常に、「自分の基準」でプレーし続けることができるのです。
- 自分が得意なショットを信じ、それを軸に組み立てる
- 自分にとって心地よいリズムでプレーし続ける
- 相手の雰囲気に惑わされず、自分の戦術を貫く
基準を持つための具体的方法
「自分の基準」を持つためには、まず「自分のテニスとは何か」を明確にする必要があります。
ここでは、「自分の基準」を明確にするための4つのステップをご紹介します。
ステップ1: 自分の強みを知る
自分にとっての「武器」や「得意なパターン」を紙に書き出してみましょう。例えば:
- 強いフォアハンド
- 高い確率で入るファーストサーブ
- 粘り強いラリー力
- 前衛での反応の速さ・決定力
これらが、あなたの「基準」の土台となります。
ステップ2: 勝利パターンを分析する
過去に勝利した試合を思い出し、どういうプレーで勝てたかを分析します。
- どんなショットを使って得点できたか
- どういうリズムで試合を進めたか
- 相手のどんな弱点を攻められたか
これらが、あなたの「基準」の核心部分です。
ステップ3: 試合前のゲームプランを作る
試合前に、自分の基準に基づいた具体的な「ゲームプラン」を立てます。
- 第一の戦術(最も自信のあるプレースタイル)
- 第二の戦術(第一の戦術がうまくいかないときの代替案)
- 自分が守るべきリズム(サーブ間のリズム、ポイント間の休憩時間など)
これが、試合中の「指針」となります。
ステップ4: 「リマインダー」を用意する
試合中に自分の基準を思い出すための「リマインダー」を用意します。これは言葉やジェスチャーなど、自分だけの合図です。例えば:
- トスアップ前に「自分のテニス」と心の中で唱える
- ポイント間に深呼吸しながら「リズム」と思い出す
- タオルを握る時に「基準」を思い出す
こうした具体的なステップを踏むことで、「自分の基準」が明確になり、試合中でもそれを保ちやすくなります。
aimでの実践例
aimでは、選手一人ひとりの「自分の基準」を見つけ出し、それを強化するトレーニングを行います。
例えば、ある中学生の選手は「粘り強さ」を自分の基準としています。どんなに苦しい展開でも、一球一球を大切に粘り続けるテニスが彼の強みです。
試合前には常に「今日の自分の基準は『粘り』」と確認し、試合中も「粘る」という言葉を自分に言い聞かせるようにしています。
こうした意識的な取り組みにより、強豪校との対戦でも自分のテニスを貫き、相手の勢いに飲まれることなく戦えるようになってきています。
2. “相手の強さ”を受け入れる
意外に思えるかもしれませんが、「相手が強いことを認める」ことも、相手に飲まれないための重要な要素です。
- 相手が強いのは当然のこと
- 相手にも武器があるのは当たり前
- 相手が攻めてくるのは自然なこと
こうした事実を冷静に受け入れることで、「相手に驚かない」「必要以上に怯えない」メンタルを育てることができます。
なぜ「受け入れる」ことが大切なのか?
相手の強さを否定したり、過小評価しようとしたりすると、実際の試合で相手の強いプレーに直面したときに「予想外」のショックを受けてしまいます。このショックが、「飲まれる」きっかけになることが多いのです。
逆に、相手の強さをあらかじめ認識し受け入れておくことで、試合中に「想定内」として冷静に対応できるようになります。
「受け入れる」ための具体的方法
方法1: 事前の情報収集と分析
可能な限り、相手の情報を事前に集め、分析しておきましょう。
- 得意なショットは何か
- プレースタイルはどういうものか
- メンタル面の特徴はあるか
知らないものは怖いですが、知っていれば「想定内」として受け止められます。
方法2: 「相手の強さ」と「自分の対策」をセットで考える
相手の強さを認識したら、それに対する「自分の対策」もセットで考えることが重要です。
- 「相手のサーブは強いが、私はリターンが得意」
- 「相手はパワーがあるが、私は粘り強い」
- 「相手は感情的になるが、私は冷静さを保てる」
このように、相手の強さを認めつつも、自分の対抗策を持つことで、過度の恐れや萎縮を防ぐことができます。
方法3: 「ベストを尽くす」という視点に切り替える
相手がどれほど強くても、自分にできるのは「ベストを尽くす」ことだけです。
- 結果ではなく「プロセス」に焦点を当てる
- 「勝ち・負け」ではなく「どう戦うか」を考える
- 「相手に勝つ」より「自分のベストを出す」ことを目標にする
こうした視点の切り替えにより、相手の強さに圧倒されることなく、自分自身の戦いに集中できるようになります。
プロから学ぶ「受け入れる」姿勢
大坂なおみ選手は、対セリーナ・ウィリアムズ戦について、「もちろん彼女は伝説的な選手。でも私もコートに立っている理由がある」と語りました。相手の偉大さを認めながらも、自分の存在意義を肯定するこの姿勢は、「相手の強さを受け入れる」絶妙なバランスを示しています。
また、錦織圭選手も「(トップ選手と対戦する時は)彼らの強さを認めた上で、自分のテニスをする」とインタビューで答えています。相手を尊重しつつも、自分のプレーを信じる姿勢が伝わってきます。
3. ポジティブな自己対話をする
試合中、特に苦しい場面や心が折れそうなときに、大きな影響を与えるのが「自分にどう語りかけるか」という「自己対話」です。
- 「もうダメだ、相手が強すぎる」
- 「このまま負けてしまう」
- 「みんながみている、恥ずかしい」
こうしたネガティブな自己対話が続くと、実際のプレーにも悪影響を及ぼし、どんどん相手に飲まれていく悪循環に陥ります。
反対に、
- 「大丈夫、自分のプレーをすればいい」
- 「相手に惑わされず、自分のリズムでいこう」
- 「次の1ポイントに全力を注ごう」
といったポジティブな自己対話は、苦しい状況でも自分を保ち、「相手に飲まれない強さ」を育てる大切な要素となります。
自己対話の力を科学的に理解する
スポーツ心理学の研究によれば、「自己対話(セルフトーク)」は選手のパフォーマンスに直接的な影響を与えることが明らかになっています。
特に注目すべきは、ネガティブな自己対話はパフォーマンスを著しく低下させる一方、ポジティブな自己対話は不安を軽減し、集中力を高め、自信を強化する効果があるという点です。
つまり、「相手に飲まれそうになったとき」に、意識的にポジティブな自己対話を行うことは、科学的にも効果が証明されている強力なメンタル技術なのです。
効果的な自己対話のための具体的方法
方法1: パーソナライズされた「キーワード」を用意する
あなたが試合中に自分を鼓舞するための「キーワード」を3〜5個用意しましょう。例えば:
- 「集中」
- 「自分のテニス」
- 「今ここ」
- 「一球入魂」
- 「リズム」
これらの言葉は、あなた自身に強く響くものである必要があります。定期的に見直し、本当に効果のある言葉に絞り込んでいくといいでしょう。
方法2: プレー前のポジティブなセルフトーク
サーブを打つ前、リターンの構えに入る前など、プレーの直前に短いポジティブなフレーズを心の中で唱えます。例えば:
- サーブ前:「確実に、力強く」
- リターン前:「見極めて、反応する」
- ラリー中:「一球一球、集中」
こうした具体的なフレーズが、プレーの質を高め、相手の勢いに飲まれることを防ぎます。
方法3: 「再解釈」のテクニック
苦しい状況を、ポジティブに再解釈するテクニックも効果的です。例えば:
- 「ピンチだ」→「ここから逆転するチャンスだ」
- 「相手が強い」→「良い挑戦の機会だ」
- 「プレッシャーを感じる」→「大切な試合だからこそ集中できる」
このような「再解釈」により、同じ状況でも心理的な影響が大きく変わります。
aimでの実践例
aimでは、選手一人ひとりの「ポジティブセルフトーク集」を作るという取り組みを行います。
これは、各選手が試合中に自分を鼓舞するために使える言葉やフレーズを集めたものです。練習中から意識的に使うことで、試合本番でも自然とポジティブな自己対話ができるよう訓練しています。
ある高校生の選手は、「落ち着いて」「見て打つ」「一球集中」の3つの言葉を自分の「セルフトーク集」として選びました。以前は相手の勢いに飲まれやすかった彼女も、この取り組みを継続したことで、プレッシャーのかかる場面でも自分を保てるようになってきています。
実例:「飲まれない強さ」を身につけた選手たち
ここまで理論的な面からお話ししてきましたが、実際に「相手に飲まれない強さ」を身につけた選手たちの例をご紹介します。
中学生Aくんの物語:「自分の基準」を見つけた少年
中学2年生のAくんは、技術的には高いレベルを持ちながらも、強い相手と対戦すると途端に萎縮し、自分のプレーができなくなるという課題を抱えていました。特に、声の大きな相手や感情表現の激しい相手に対しては、すぐに「飲まれて」しまっていました。
Aくんに対して私たちが提案したのは、「自分の基準」を明確にすることでした。彼の強みは「正確なグラウンドストローク」と「冷静な状況判断」。これらを活かした「自分のテニス」を定義し、試合前には必ずその「基準」を確認するようにしました。
また、試合中に「基準」を思い出すための「リマインダー」として、ポイント間にラケットのグリップを握り直す動作を取り入れました。この単純な動作が、「自分の基準に戻る」という意味を持つようになったのです。
徐々にですが、Aくんは相手の勢いに飲まれることなく、自分のテニスを貫けるようになってきました。最近の大会では、以前なら圧倒されていたような強豪選手を相手に、終始冷静なプレーで勝利を収めることができました。
40代女性Bさんの物語:「相手の強さを受け入れる」ことを学んだ主婦
テニス歴5年のBさんは、地域のダブルス大会に出場する際、いつも同じパターンに陥っていました。「強い相手だと聞くと緊張して眠れなくなり、試合当日はすっかり委縮してしまう」というのです。
Bさんには、「相手の強さを受け入れる」ワークを提案しました。
まず、対戦相手について知っていることをすべて書き出します。「強いサーブを持っている」「ネットプレーが得意」など。
次に、それぞれに対する「自分たちの対策」を考えます。「サーブに対しては早めに構える」「ネットプレーには高めのボールで対応」など。
最後に、「どんなに相手が強くても、自分たちにできることは変わらない」ということを確認します。
この取り組みにより、Bさんは相手の強さを「脅威」ではなく「挑戦」と捉えられるようになってきました。「相手が強いのは当たり前。でも、私たちにも強みがある」という考え方が定着し、以前より自信を持ってコートに立てるようになったのです。
高校生Cさんの物語:「ポジティブな自己対話」を身につけた女子選手
高校のテニス部に所属するCさんは、技術的には高いレベルながら、メンタル面に課題を抱えていました。特に、流れが悪くなると「もうダメだ」「負けるかも」といったネガティブな思考パターンに陥りやすい傾向がありました。
Cさんに対しては、「ポジティブな自己対話」の練習を重点的に行いました。
まず、試合中によく浮かぶネガティブな言葉を全て書き出してもらいます。次に、それぞれに対応する「ポジティブな言い換え」を考えます。
例えば:
- 「もうダメかも」→「一球一球、集中あるのみ」
- 「相手が強すぎる」→「良い挑戦の機会だ」
- 「みんなが見ている」→「自分のテニスを見せよう」
このポジティブフレーズを、練習中から意識的に使うトレーニングを行いました。
最初は違和感があったようですが、継続することでCさんの頭の中の声が少しずつ変化していきました。最近の大会では、第1セットを大差で落としたにもかかわらず、ポジティブな自己対話を続けることで精神的な安定を保ち、見事逆転勝利を収めることができました。
最後に──相手に飲まれない強さとは
これまでの内容を踏まえ、「相手に飲まれない強さ」とは何かを改めて考えてみましょう。
それは、単に「相手の影響を受けない」ということではありません。テニスは対人スポーツであり、相手からの影響を完全に断ち切ることは不可能です。
真の「飲まれない強さ」とは、「自分を信じる力」と「相手に左右されない軸」を持ちつつ、相手と自分、両方の存在を認めた上で、自分のプレーを貫く力ではないでしょうか。
そのためには、
- 自分の基準を明確にする
- 相手の強さを受け入れる
- ポジティブな自己対話を続ける
これらを意識した練習と経験の積み重ねが必要です。
その強さは、テニスを超えて
最後に付け加えたいのは、この「相手に飲まれない強さ」は、テニスコートの中だけでなく、人生のあらゆる場面で価値を持つということです。
仕事、学校、人間関係…どんな場面でも、「自分の軸を持ちながら、他者の存在も尊重する」というバランス感覚は、豊かな人生を送るための重要な要素となります。
テニスという競技を通じて、この普遍的な強さを身につけていただければ、私たちコーチ冥利に尽きます。
さあ、またコートで会いましょう。
相手に飲まれず、自分を信じる強さを育てるために。 僕たちは全力で応援します。
aim TENNIS ACADEMY 代表 まさたこ
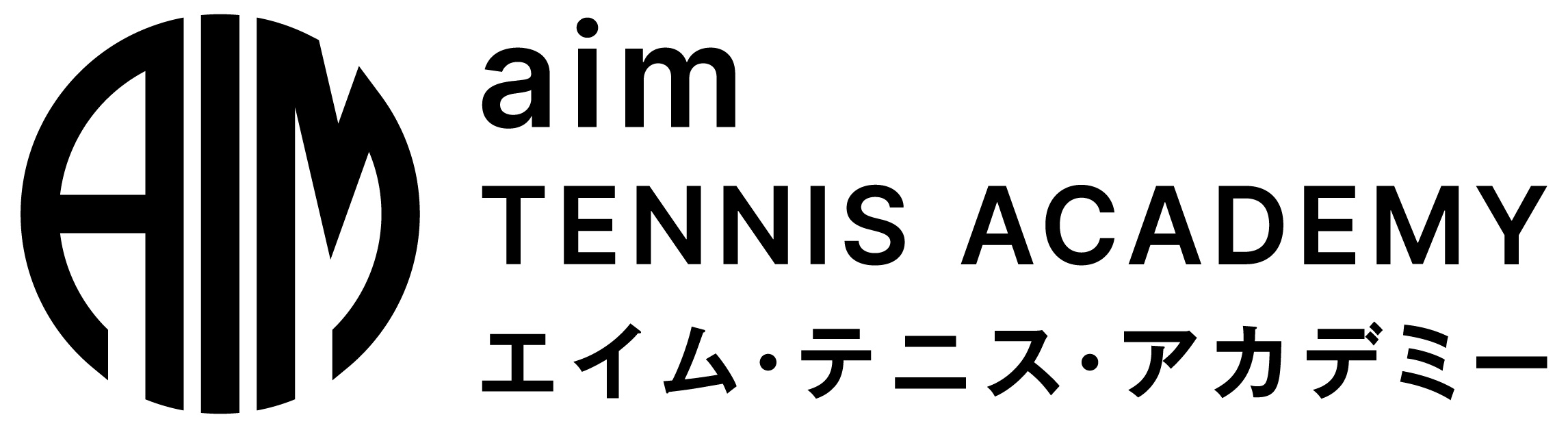







コメント