 まさたこ
まさたここんにちは。aim TENNIS ACADEMY代表の、まさたこです。
今日は、テニスプレーヤーなら誰もが経験する「大事な場面での緊張」について、深く掘り下げてお話ししたいと思います。
この記事を読み終えるころには、あなたの中で「緊張」に対する見方が変わり、それを味方につける方法が見えてくることを願っています。
1. 緊張することを肯定する——それは本気の証
緊張するのは、悪いことじゃない
まず、これだけははっきり言っておきたい。
「緊張するのは、悪いことじゃない。」
むしろ、緊張できることは素晴らしいことだと私は確信しています。
なぜなら、緊張するということは、それだけその瞬間が「自分にとって大切な場面」だという証拠だからです。
- 重要な試合のマッチポイント
- ライバルとの真剣勝負
- ペアと共に迎える大事な1ポイント
- 応援してくれる人たちの前でのプレー
そんな瞬間に緊張するのは、「自分が本気でその場に立っている証」なのです。
逆に、全く緊張しないということは、その場面に真剣に向き合っていない可能性もあります。「どうでもいい」と思っていることに緊張は生まれないのです。
だから、まずはその緊張という感情を否定せず、大切にしてほしいと思います。
一流選手も緊張している
多くの人は、プロ選手や一流のアスリートは「緊張しない」と思っているかもしれません。しかし、それは大きな誤解です。
テニス界のレジェンド、ロジャー・フェデラーでさえ、「グランドスラムの決勝では、いつも最初の数ゲームは緊張でラケットを握る手が震える」と語っています。
また、20回以上のグランドスラム優勝を誇るラファエル・ナダルも、「緊張しない試合はない。ただ、その緊張と共に戦うことを学んだ」と述べています。
彼らのような偉大な選手でさえ緊張するのです。違いは、その緊張をコントロールし、パフォーマンスに活かす術を身につけているということです。
私自身の緊張体験
ここで、私自身の経験をお話ししたいと思います。
大学時代、北海道大会ベスト8に進出したときのことです。相手は高校時代からの強豪選手。会場には多くの観客が集まり、私の両親も応援に来ていました。
第1ゲームのサービスゲーム。トスを上げる手が震え、1投目、2投目とミスしてしまいました。3投目のトスでようやくサーブを打ちましたが、ダブルフォルトで失点。その後も緊張からミスを連発し、あっという間に0-3とリードされてしまいました。
私はベンチに座り、深呼吸をしながら自分に言い聞かせました。 「この緊張は、自分が本気だからこそ。逃げずに向き合おう」
その後のプレーは劇的に変わりました。結果的には惜しくも負けてしまいましたが、フルセットの接戦まで持ち込むことができました。
この経験から私は、「緊張を恐れるのではなく、受け入れる」ことの大切さを学びました。
科学的に見た「緊張」の正体
緊張の正体を知ることも、それと向き合う上で大切です。
緊張すると、体内では「闘争・逃走反応」と呼ばれる生理反応が起こります。アドレナリンやコルチゾールといったホルモンが分泌され、心拍数の上昇、呼吸の速さの変化、筋肉の緊張などが生じます。
これは本来、危険な状況に直面したときに「戦うか逃げるか」の判断を素早くするための、人間の生存本能なのです。
つまり、緊張は私たちの身体が「今から大事な場面だ」と認識し、最高のパフォーマンスを発揮するための準備をしている状態とも言えるのです。
2. 緊張を”敵”にしないための具体策
緊張すること自体は自然なことですが、過度の緊張がプレーに悪影響を及ぼすこともまた事実です。
- サーブが入らなくなる
- フットワークが重くなる
- 判断が遅れる
- ミスが増えて自信を失う
こうした状況を防ぐために、実践的な対処法をご紹介します。
呼吸を整える——最もシンプルで効果的な方法
緊張すると、どうしても呼吸が浅く速くなりがちです。これが心拍数の上昇や筋肉の過緊張を招き、プレーに悪影響を及ぼします。
そこで効果的なのが、意識的な深呼吸です。
4-7-8呼吸法
- 鼻から4カウントかけて息を吸う
- 7カウント息を止める
- 口から8カウントかけてゆっくりと息を吐く
- これを3〜5回繰り返す
この呼吸法は、自律神経のバランスを整え、副交感神経の活動を高めることで、過度の緊張状態から体を落ち着かせる効果があります。
aimでの実践例
aimのレッスンでは、試合形式の練習の前に必ずこの呼吸法を取り入れてます。最初は「こんなので本当に変わるの?」と半信半疑だった生徒たちも、実践を重ねるうちにその効果を実感するようになりました。
ある中学生の生徒は、この呼吸法を試合前のルーティンに取り入れたことで、以前よりも格段に落ち着いたプレーができるようになったと言います。
「息を整えると、頭の中も整理される感じがします。何をすべきか、どう動くべきかが明確になるんです」
“次の1球”に集中する——「今、ここ」の力
緊張は、多くの場合、過去のミスや未来の結果に意識が向くことで強まります。
「さっきのミスを取り返さないと…」 「このままだと負けてしまう…」 「この試合に負けたら次の大会に出られない…」
こうした思考が、現在のプレーを台無しにしてしまうのです。
テニスは“今この瞬間“が勝負のスポーツ。過去でも未来でもなく、「次の1球に集中する」ことが、緊張を和らげる鍵となります。
ワンポイントフォーカステクニック
これは、プロスポーツ選手のメンタルコーチが実践している方法です。
- プレーの合間に、コートの特定の場所(例:ネットの中央)に視線を向ける
- その1点を見つめながら、深呼吸を1回行う
- 「次の1球だけ」と心の中で唱える
- プレー再開
この単純な行動が、過去や未来への思考から「今ここ」に意識を引き戻す効果があります。
フォーカスワードの活用
緊張した場面では、自分自身を「今」に引き戻すための「フォーカスワード」も効果的です。
例えば、
- 「集中」
- 「今この球」
- 「一球入魂」
など、自分にとって意味のある言葉を決めておき、緊張したときに心の中で唱えます。
私がコーチングする高校生の男子選手は、試合中に緊張するとすぐに「次、次」と小さく呟く習慣をつけました。過去のミスを引きずらず、次の1球に意識を切り替えるこの単純な言葉が、彼のプレーを安定させる大きな要因となっています。
自分のルーティンを持つ——安定と安心の源
プロ選手がサーブ前に必ず同じ動きをするのは、単なる習慣ではありません。それは、どんな状況でも心を落ち着かせ、集中力を取り戻すための「儀式」なのです。
ラファエル・ナダルの独特なルーティン(髪を触り、服を整え、ボトルを並べる…)は有名ですが、彼はそれについて「自分をコントロールするために必要な行動」と語っています。
効果的なルーティンの作り方
効果的なルーティンには、以下の3つの要素が含まれていると良いでしょう。
- 身体的動作:グリップを握り直す、ラケットの面を整える、帽子を直すなど
- 呼吸:深呼吸を意識的に行う
- 集中のための言葉:先ほどのフォーカスワードを唱える
これらを組み合わせた自分だけのルーティンを作り、練習から意識的に取り入れることで、試合の緊張場面でも自然と体が動くようになります。
ルーティンが生んだ奇跡
aimの生徒の中に、緊張すると手が震えてサーブが入らなくなる一般女性がいました。どんなに技術練習をしても、試合本番ではその症状が出てしまいます。
そこで彼女と一緒に考えたのが、「5つのS」というサーブ前ルーティンでした。
- Stand(立ち位置を確認)
- See(相手と狙うコースを見る)
- Smile(軽く微笑む)
- Slow breath(ゆっくり呼吸)
- Swing(振り抜く)
最初は意識的に行っていたこのルーティンも、繰り返すうちに体に染み込み、今では無意識に行えるようになりました。結果として、試合でのサーブ成功率が格段に上がり、昨年の大会では優勝という成績を収めることができたのです。
準備と練習——緊張に備える最良の方法
緊張への対処で最も効果的なのは、実は「十分な準備をしておくこと」です。
しっかりと練習を積み、技術的な土台ができていれば、多少緊張しても基本的なプレーは崩れにくくなります。また、様々な状況を想定して練習しておくことで、「初めて」の感覚による緊張も軽減できます。
プレッシャー下での練習法
通常の練習に、意図的に「プレッシャー要素」を取り入れることで、試合本番での緊張に強くなります。
例えば、
- 「このサーブが5本中3本入ったら練習終了、そうでなければ追加練習」といった条件を設ける
- 練習試合の最終ゲームだけ、周りの人に見てもらう
- 体力が落ちてきた練習終盤に、集中力を要する課題に取り組む
こうした「緊張感のある練習」を日頃から取り入れることで、本番での緊張にも対応できる心と体を作ることができます。
3. 緊張を”力”に変えるマインドセット
緊張を完全になくすことは難しいですし、必要でもありません。大切なのは、その緊張を「パフォーマンスを下げる敵」ではなく「力を引き出す味方」と捉えるマインドセットを持つことです。
緊張を「興奮」と捉え直す
心理学の研究によれば、「緊張している」と「興奮している」という感情は、生理学的にはほぼ同じ状態だと言います。違いは、それをネガティブに捉えるかポジティブに捉えるかという「解釈」の違いなのです。
言葉の力を活用する
緊張を感じたとき、「緊張する」という言葉ではなく、「興奮している」「準備ができている」などのポジティブな言葉で自分の状態を表現してみましょう。
「私は緊張している」→「私は興奮している」 「私は不安だ」→「私は挑戦する準備ができている」
この「リフレーミング(捉え直し)」が、実際のパフォーマンスを向上させることが研究で証明されています。
自己対話の重要性
緊張した場面では、頭の中で自分自身に語りかける「自己対話」が特に重要になります。
ネガティブな自己対話:
- 「ミスしないように気をつけよう」
- 「失敗したらどうしよう」
- 「みんなが見ている、恥をかきたくない」
ポジティブな自己対話:
- 「自分のテニスを思い切り楽しもう」
- 「この緊張は、私が本気だからこそ感じるもの」
- 「この1ポイントに全てを懸けよう」
緊張した場面で、どちらの自己対話を選ぶかで、プレーの質は大きく変わってきます。
「ゾーン」に入るための緊張活用法
スポーツ心理学では、最高のパフォーマンスが発揮される状態を「ゾーン(フロー)」と呼びます。このゾーンに入るためには、実は「適度な緊張感」が必要だと言われています。
緊張が少なすぎると集中力に欠け、多すぎるとプレーが硬くなる。最高のパフォーマンスは、その中間にある「適度な緊張状態」で発揮されるのです。
YerkesDodsonの法則
これは心理学で知られる法則で、「パフォーマンスと覚醒(緊張)レベルの関係」を示したものです。適度な緊張感が、最高のパフォーマンスを引き出すという考え方です。
大事なのは、自分にとっての「適度な緊張レベル」を知ることです。それは人によって異なります。自分がベストのプレーをしたときの緊張レベルを思い出し、それを基準に調整していくことが大切です。
プロアスリートの緊張活用法
多くのプロアスリートは、緊張を「敵」ではなく「必要な要素」と捉えています。
テニスの大坂なおみ選手は、「大事な試合前は緊張で眠れないことも多い。でも、それは自分が準備できている証拠だと思うようにしている」と語っています。
また、錦織圭選手も「緊張は避けられないもの。大切なのは、それとどう向き合うか」と言います。
彼らは緊張を否定せず、むしろそれを「パフォーマンスを高める燃料」として活用しているのです。
「失敗してもいい」という勇気
緊張がパフォーマンスを下げる最大の理由の一つは、「失敗への恐れ」です。「ミスしたらどうしよう」「負けたらどうしよう」という思いが、体を硬くし、消極的なプレーを招きます。
このような状況を打破するには、「失敗してもいい」という勇気が必要です。
「プロセス」に焦点を当てる
結果ではなく「プロセス」に焦点を当てることで、失敗への恐れを軽減できます。
「勝つ・負ける」ではなく、「自分のテニスをどれだけ発揮できるか」「学んだことをどれだけ実践できるか」という視点でプレーに臨むことで、結果への執着から解放されます。
実例:最高のプレーは「解放された心」から生まれる
aimの生徒の中に、試合になると極度に緊張し、普段の半分も力を発揮できない中学生がいました。どんなに技術練習を積んでも、本番での緊張を克服できずにいました。
ある日の試合で、彼には「今日は結果を気にしないで、とにかく思い切り打ってみよう」と提案しました。「負けてもいい、ミスしてもいい、ただ自分の打ちたいショットを打とう」と。
最初は戸惑っていた彼でしたが、徐々に肩の力が抜け、普段の練習では見られないような大胆なショットを打ち始めました。結果は勝利。しかも、相手を圧倒する内容でした。
試合後、彼はこう語りました。「不思議でした。『ミスしてもいい』と思ったら、逆にミスが減って、思い切り打てるようになった。緊張はしていたけど、それが邪魔にならなかった」
この経験は、彼にとって大きな転機となりました。「失敗してもいい」という勇気が、最高のパフォーマンスを引き出すこともある——この真理を体感したのです。
4. 本気で戦う人への力強いメッセージ
ここまで、緊張との付き合い方について様々な角度からお話ししてきました。最後に、日々テニスと真剣に向き合い、時に緊張に苦しみながらも前に進もうとしているあなたへ、私からのメッセージを送りたいと思います。
緊張することの意味——あなたの本気の証
もし今、試合前や大事な場面で緊張しているあなたがいるなら、その気持ちは、**「あなたが本気で戦っている証」**です。
多くの人が、夢や目標、挑戦を途中で諦めてしまいます。何かを成し遂げようとせず、ただ日々を過ごしていれば、確かに緊張することはないでしょう。
しかし、あなたは違います。目標に向かって歩み、壁に挑み、時に苦しみながらも立ち向かっている。その姿勢こそが、「緊張する瞬間」を生み出しているのです。
だから、その緊張を恐れず、むしろ誇りに思ってください。それは、あなたが「挑戦者」として生きている証なのですから。
緊張と共に成長する
緊張との付き合い方は、一朝一夕で身につくものではありません。それは、テニスの技術と同じく、経験と練習を通じて徐々に磨かれていくものです。
今日ご紹介した方法を、ぜひ練習や試合の中で実践してみてください。最初はうまくいかないこともあるでしょう。それでも構いません。大切なのは、「緊張と向き合う姿勢」を持ち続けることです。
そうすれば、少しずつですが確実に、緊張をコントロールし、それを力に変える術を身につけていくことができるでしょう。
強さとは、緊張しないことではない
真の強さとは、緊張しないことではありません。緊張しながらも、それに打ち勝ち、自分の力を発揮する勇気を持つことです。
テニスの王者と呼ばれる選手たちも、重要な場面では緊張します。彼らが素晴らしいのは、緊張しないからではなく、緊張と共に戦う術を身につけているからなのです。
あなたもまた、その道を歩んでいる途上にいます。一歩一歩、確実に前進していきましょう。
最後に——緊張している自分を愛する
最後に、最も大切なことをお伝えします。
「緊張している自分を、もっと好きになってください」
緊張している自分は、本気で何かに取り組み、挑戦し、成長しようとしている姿です。それは愛おしく、尊いものです。
その気持ちを胸に、一歩踏み出してみてください。僕たちaimは、そんな”本気の瞬間”を全力で応援します。
緊張している自分を、もっと好きになれる日が、きっと来るはずです。いや、その日は既に、ここにあるのかもしれません。
さあ、コートでお待ちしています。
aim TENNIS ACADEMY 代表 まさたこ
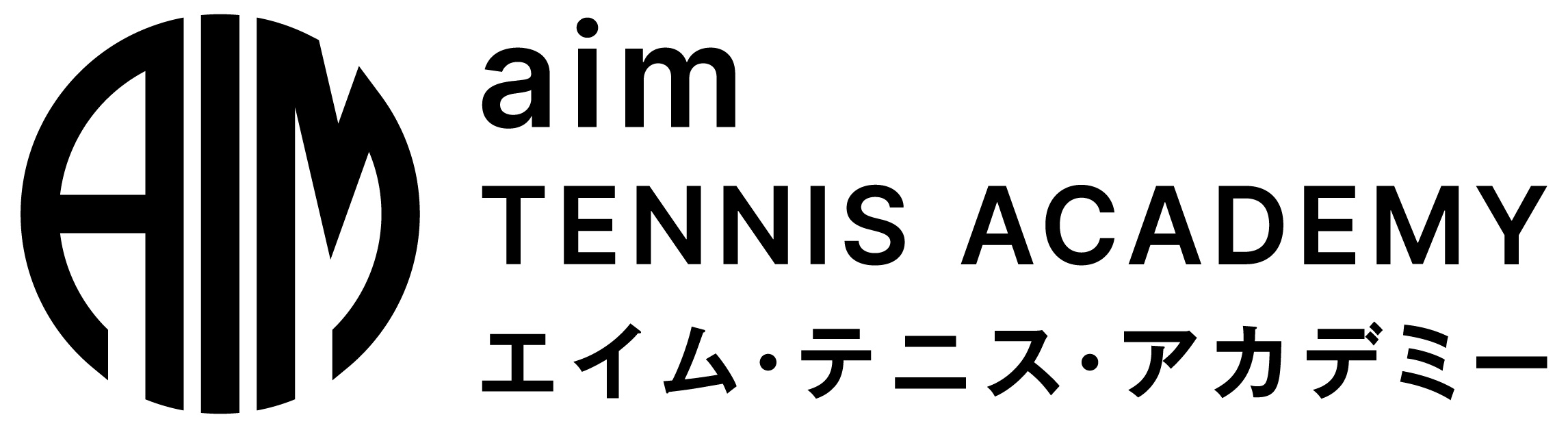







コメント